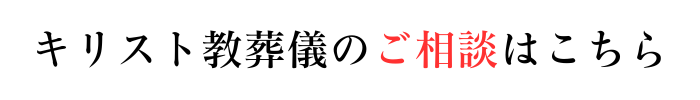仏教では故人が亡くなられた節目の年に法事を行います。一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌などです。
こうした節目の年に故人の命日などに合わせて親族で集まり、僧侶を読んで読経などをしてもらう、いわゆる「法要」を行う習慣が仏教にはあるのです。
キリスト教では「記念会」、でもその意味は…
時々教会で葬儀を執り行った故人の親族の方から、「キリスト教でもこのような習慣はあるのですか?」といった質問をいただきます。結論から言えば、キリスト教では何か節目の年を決めて必ず「法要」のようなものを行わなければならないという習慣はありません。それでも親族で集まって、故人を偲びたいという場合は「記念会」というのを行います。教会などどこか集まれる場所で礼拝を行い、その後茶話会や食事会などをしたりして故人を偲ぶひと時を持ちます。
仏教の「法要」は亡くなった方の魂を供養するという意味合いを持ちますが、キリスト教の「記念会」はそのような意味を持ちません。そのような供養をしなくても、故人は既に救われて神様の御許で安らかに永遠の命に憩っておられると信じるのがキリスト教です。
グリーフワークとしての意義再考
ただ五十回忌まで親族で集まる機会を持つ仏教の「法要」には、牧師である私個人は「なるほど」と考えさせられるところもあります。愛する方を失った悲しみを消化するのに、人はそれくらいの時を必要とするということでしょうか。節目節目に親族で集まって故人を偲ぶ機会を持つということに、残された者の慰め、グリーフワークとしての意義を感じます。

キリスト教においても「記念会」をもっと頻繁に行って、故人を偲ぶ機会を多く持つということをしても良いかもしれません。キリスト教で葬儀を挙げられた方で「記念会」をお考えになる方は、葬儀を司式された牧師にご相談いただければ幸いです。あるいは「ともなる」にもご相談ください。