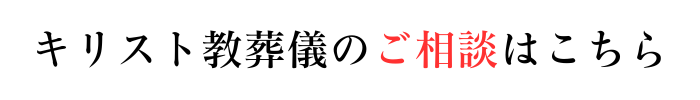先日、出張でバングラデシュへ出かけてきました。地方にある経済的に恵まれていない村へ行き、村の中にあるプレスクール(小学校就学前の子たちが通う幼稚園や保育所のような学びの場)を支援するために訪問してきました。村へは車で移動するのですが、ある村へ出かけた時に、道の向こうからご遺体を乗せたベッドのフレームのような物を6人くらいの男性が担ぎながら歩いて来て、すれ違いました。それを見ながら、「バングラデシュではどういう葬儀を行っているのだろう」と思い、バングラデシュの葬儀について調べてみました。
バングラデシュの葬儀事情-主にイスラム教
バングラデシュは国民の9割がイスラム教、1割がヒンドゥー教、仏教、キリスト教は1割未満という割合だそうです。イスラム教では、人が亡くなると24時間以内に埋葬するそうです。火葬ではなく土葬とのことです。葬儀は土葬を行った後に行うらしく、日本のようにご遺体が前にあるわけではなく、また火葬場の都合で葬儀の日程が決まるわけでもありません。イスラム教の葬儀は基本的にモスクで行われます。モスクでは厳格なルール(規則)があり、故人の家族であれば、モスクでの葬儀に参列できるそうですが、親しい知り合いであっても、女性はモスクでの葬儀に参列することは許されず、女性は自宅にて故人を弔うそうです。
葬儀の4日後にはKulkhaniと呼ばれる祭礼が開催され、イスラムの僧侶と聖職者と親族、葬儀を手伝ってくれた方すべてを招待するそうです。さらに、30日後にはChollishaという儀式が行われます。この際は、僧侶や親族をはじめ、友人や近所の人などが招かれて、故人への祈りが捧げられます。いずれの儀式でも参列者にはバングラデシュ料理などが振る舞われます。
ネパールの葬儀事情-主にヒンドゥー教
これまで、私はネパールに5回旅行で訪れましたが、私が必ず行く場所があります。それはネパールの首都カトマンズにあるパシュパティナート寺院です。パシュパティナート寺院はネパールで最大のヒンドゥー教寺院で、破壊と再生を司るシヴァ神を祭る寺院です。パシュパティナートはシヴァ神を祭る寺院というだけではなく、野外葬儀場という側面もあります。ガンジス川へと続くバグマティ川の河岸に建つ葬儀場で、遺体は聖なる川の水で清められた後、荼毘に付されます。特に火葬炉がある建物があるのではなく、川岸にある火葬台の上に藁を敷き、その上に遺体を置いてそのまま火葬します。家族や参列者でなくても、パシュパティナート寺院内で火葬している対岸から火葬の様子を見ることができます。私はそこでよく火葬の様子を見ながら、生死について考える時間を持っています。そこでの3時間ほどかけての火葬が終わると、遺灰はバグマティ川を流れ、やがて合流するガンジス川へと流れて行きます。

ヒンドゥー教徒の火葬は、喪主が海外在住などの特別な事情がない限り、死亡から24時間以内と非常に迅速に行われるそうです。ネパールの喪の色は日本と違って白であり、喪主とその家族は白装束に身を包みます。そして男性は髪を剃り、女性は普段は結っている髪を下ろします。喪主と家族以外の参列者については、特に服装の決まりはないそうです。
火葬が終わると、ここから様々な儀式が始まります。毎日ヒンドゥー教の司祭が家を訪れ、清めの儀式を行い、決められた食材のみを使った食事を取ります。歌や踊りの禁止など、その他にも様々なタブーがあり、地域によって風習に差はあるようですが、このような生活を13日間続けると言います。そして、輪廻転生を願うヒンドゥー教徒に、お墓を持つ習慣はありません。
自分の死について考える時を持ちましょう
日本では、私は牧師であり、クリスチャンなので、キリスト教の葬儀に参列したり、司式することがほとんどですが、旅先でその国に生きた方の最期の時に出会い、さまざまな宗教やその地域特有の方法で大切な故人を見送る場面に直面し、さまざまな死生観や最期の見送り方があることを思わされます。宗教や方法、死生観は違えど、大切な家族や友人を大切に送ろうとする想いや故人を偲ぶために行われる一つ一つの儀式や祭礼、集会に敬意を持ちたいと思います。

キリスト教の葬儀(前夜式、告別式)や納骨式、○周忌など故人を天国に見送る地上での最期の時、故人を偲ぶ時が持たれます。日本で行われる葬儀の9割が仏式と言われているので、クリスチャンでない方がキリスト教式の葬儀に参列する機会はあまりないかもしれません。それでも、初めてキリスト教式の葬儀に参列された方々から、「とても良かったです」、「温かい葬儀に感動しました」という声をいただくことが多くあります。それは、故人が大切にされていた聖書の意味や故人の愛唱讃美歌を讃美したり、説教で故人の在りし日の略歴や生き方を、聖書箇所を交えつつ、そこに集う方々にもわかる言葉で共有するからなのかもしれません。
また、キリスト教では、地上での歩みを終えると、天国へと旅立つことを意味します。地上での別れを悲しみつつも、天国での再会という希望が与えられることもキリスト教ならではの大切なメッセージです。クリスチャンでなくても、キリスト教の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、短大などに通っていた方や小さい頃に教会学校に通っていた、という方は多くいらっしゃると思います。キリスト教式で結婚式をされたご夫婦も多くいらっしゃるでしょう。そういう方々が、「地上での最期の時、キリスト教式で見送ってもらいたい」と考え、キリスト教式の葬儀を選択されることも良いのではないかと私は考えています。
日本では慌ただしく過ごす中で、なかなか自分自身の最期の時について考える時間も余裕もないですが、旅をする中で、少しゆっくり時間を取って最後の時について考える時間が与えられ、その国やさまざまな宗教の葬儀や死生観だけではなく、自分自身に向き合う時間が与えられることに感謝したいと思います。皆さんも少し時間を取って、最後の時について考えてみるのも良いのではないでしょうか。