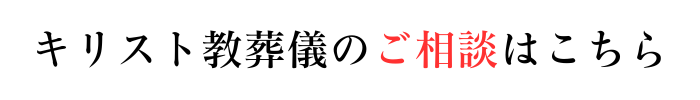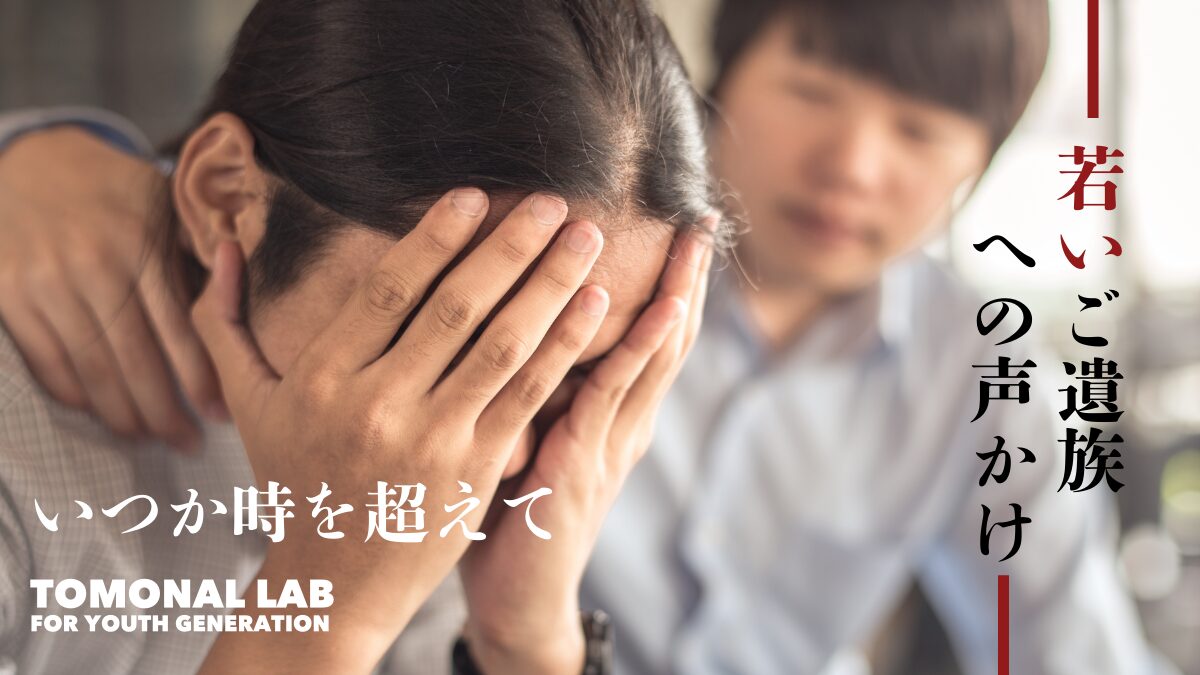若いご遺族、特に10代のころにごく近い家族、親しい友人が逝去された方に、どのように声をかければいいのでしょうか。もちろん、そのお見送りの状況はそれぞれ違いますから、「人による」というのは間違いありません。

ただ、私も小学校5年生(11歳)の時に母親が逝去しており、その時にいただいた言葉のうち、記憶に残り続けているものがあります。これをひとつの例示としてお伝えできることがあるかと思いました。また、その言葉かけの中には、普遍的な意義をもった部分もあるように今となって思い返してもいます。
母親の逝去と葬儀
私の母親は、2000年頃に40代前半で逝去しましたが、余命を自ら主治医に尋ね、死の準備をとても丁寧にしていたようです。葬儀で読まれる聖書や賛美歌の選択はもちろん、写真、残していく家族のための味噌汁の作り方、納骨場所の希望、闘病の手記まで、書き残していました。入院生活も長かったので、10歳前後の私たち兄弟(私には1学年下の弟がひとりいます)から見ても、段々とつけられる機械が増えていく様子に、直接的に話はしないけれど少しずつ死を感じている部分はあったように思います。
ただし、反抗期もそろそろ始まる…という年頃でした。友人に心配や同情をされたくない、あれこれ聞かれたくないというような、固定的な「強さ」や「普通」への思いも抱えておりました。お見舞いに病院に向かうときにも、そういった感覚はどこかあり、いつも病院で誰とも会わないよう願っていました。

そんな中で母は逝去しましたので、葬儀の間に泣くということもありませんでした。
葬儀の際に読まれた聖書は「主において常に喜びなさい」(フィリピの信徒への手紙4章4節)だったのですが、この言葉を、いわゆる「根性で泣きません!」のようなやせがまんの類のこととして受けとめているような状況だったと言えるかな、とも思い出しています。
いただいた先生からの手紙

さて、葬儀の日のことです。前の年まで担任をしてくれており、当時は少し離れた街の小学校で働いておられたY先生が、一通の手紙を「いつでもいいから読んでね」と渡してくれました。ただ、上記のような心持ちだったので、もらった当初は、なんとなく一読したくらいで机にしまい込んでいました。その様子を見ていた父親が「なんて書いてあったんだ?」と問いかけてきたのですが、それについても「まぁ普通のことだった」くらいの返答をした記憶があります。
長いときが経って
しかし、25年経つと、Y先生の書いてくれた「普通のこと」は「普遍のこと」として思い出されます。「いっぱい泣いていいんだよ」「これまでそうだったように、自然体で、自分らしさをこれからも大切に過ごしてね」という内容でした(もう少し詳細を言うと、私は当時からお店に入る時に店員さんに「こんにちは」「失礼します」とあいさつをする、少なくとも会釈する習慣があるのですが、そういう君でいてねという例話がありました)。

そして、この手紙が語ることがらは、母の葬儀で読まれた聖書の意味を確かに物語るものだったとも思い返しています。「主において常に喜びなさい」・「いっぱい泣いていいんだよ」。言葉上は反対のようでいて、悲しみをそのまま悲しめるというところに、自己肯定という命の祝福、真の喜びがあると、そのように語りかける言葉であったと理解しています。かなりの時間が経って、ありがたい声かけをしていただいていたのだと振り返っています(大変失礼なことにその手紙自体は引っ越しの際に無くしてしまっているのですが…)。
若いご遺族への声かけ
ここでお伝えしたのは私自身のひとつの事例ではありますが、Y先生の手紙は手法的にも内容的にも、いくつかの点で参考になるところがあると思いますので、当時の自分の気持ちも思い出しながら記してみます。
- 手紙という方法
先述の通り、私の場合は反抗期の始まるころでしたので、なかなか人の言葉を素直に聞けない発達段階でもありました。動転している、初めての葬儀で心がついていかないなど、一時的に聞きづらい状態になっている可能性も考えられるところです。その時すぐに「沁みる」声かけは、その言葉がどれほど優れたものであったとしても、確実にできるわけではないと思います。
遺族が成人してからなど、かなりの時間が経って(私の場合は20年以上(!))、声かけが意味を持ってくるというケースも、大人の遺族に比較して一層考えられるでしょう。少し落ち着いた時に、あるいは繰り返して声かけに触れられる可能性を残す手法はそれだけで有益と感じています。
- 正直な思い/ありきたりでもいい
Y先生の手紙の内容は、それほど特別なことが書かれていたのではありませんでした。最初に読んだとき「普通のこと」と表現した通りです。確かに「泣いてもいいんだよ」「自然体でいいんだよ」は、25年前でも普通に言われることでした。
しかし当時の私は、病院にお見舞いに行くのにも、「もし友人にばったり会ったら、あとで色々聞かれて面倒なのではないか」「変に同情を買って居づらさを感じるのではないか」と考えてしまうほどで、その精神状態は「普通」ではなかったかもしれないです。泣いても普通、病院に見舞いに行くことがあった君もそれはそれで君であり、自分らしく居たらいい、とそれほど珍しくはない声かけを正直にしてくれる存在を最も必要としている状況にあったように思い出されます(実際それを自覚し言葉化するのにはとてつもない時間を必要としたわけですが…)。
私自身の一例からおはなしいたしました。
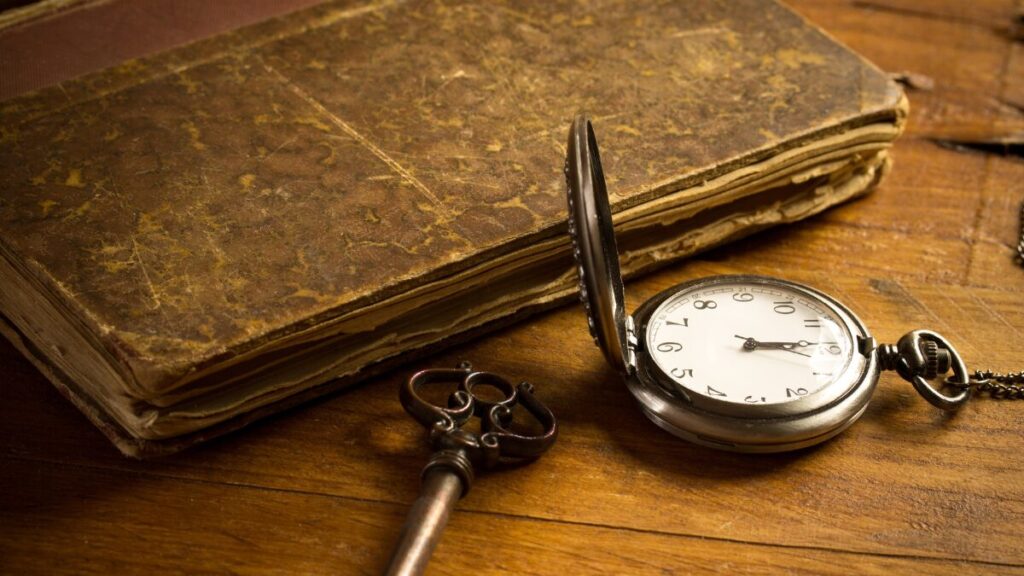
もちろんこれらは、基本的には遺族が若年層であるかどうかを問わず、有益な場面も多いだろうとも思います。当時の自分の状況を思い出したとき、特にあの年頃の自分に適切であったと感じているので、ご紹介してみました。
その場では沁みないのは当たり前、10年後、20年後にジワっと優しさを感じられたらそれでいい!とご承知いただき、正直な思い・言葉をかけてくだされば、そこに神の癒やしが、いつか時を経て働くことでしょう。