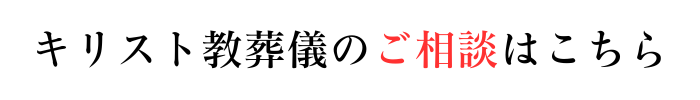誰にも訪れる人生の終末期。しかしそれがいつ、どのような形で訪れるかは誰にも分かりません。ぎりぎりまで健康でぽっくり、誰もがそのような最期を迎えたいと思うでしょう。しかし皆が皆、そのような最期を迎えられるわけではありません。もしも自分が終末期を迎えたら?その時のことを、どれだけ家族と分かちあっているでしょうか?
「価値ある生き方」としての「尊厳死」
実は1980年代以前の医療は救命と延命を重視していました。しかしその後QOL(=Quality of Life、生命の質)が叫ばれるようになり、ただ長生きすればいいというだけでなく、人間として価値ある生き方を続けることこそ大事だという意識が高まって来ました。その中で人間の尊厳を損なう形で無理に延命するのではなく、苦痛を取り除いてもらい、最期まで人間らしい人格を保ちながら死を迎えたいとする「尊厳死」の考え方が高まって来ました。

「尊厳死」というのは、自分の傷病が今の医学では治る見込みがなく、死が迫って来た時(不治かつ末期)に、たとえば胃ろうは止めてほしいとか、植物状態になった時には生命維持装置を外してほしいとかいったように、自ら「死のあり方を選ぶ権利」を持とう、そしてその権利を社会に認めてもらおうという権利運動です。誤解のないように言っておかなければなりませんが、それは例えば医師が致死薬を投与するなどして患者を直接死に至らしめる「安楽死」(direct killing)とは異なります(※日本では法律上「安楽死」は認められていません)。「尊厳死」とは、胃ろうはしない、生命維持装置を外すなど、無理な延命はしないで患者を自然な死に任せる(letting to die)ことであり、「自然な死を求める権利」、「死に至る過程を選ぶ権利」であると言えるでしょう。つまり、「人間の尊厳を保ちながら安らかな自然な死を選ぶ権利」のことです。
「リビング・ウィル」を備えましょう
私も牧師としてこれまでたくさんの人の終末期に寄り添って来ましたが、この日本の医療でも、終末期にはホスピスなどで緩和ケアを受けることができるようになったりと、かなりQOLが重視されるようになってきたのを感じています。しかしそこでも、例えばもう意識がほとんどなく、自分で口から食べることができなくなった時に栄養を点滴するかなど、ご家族が判断を迫られて葛藤に苦しむ場面をたくさん見てきました。
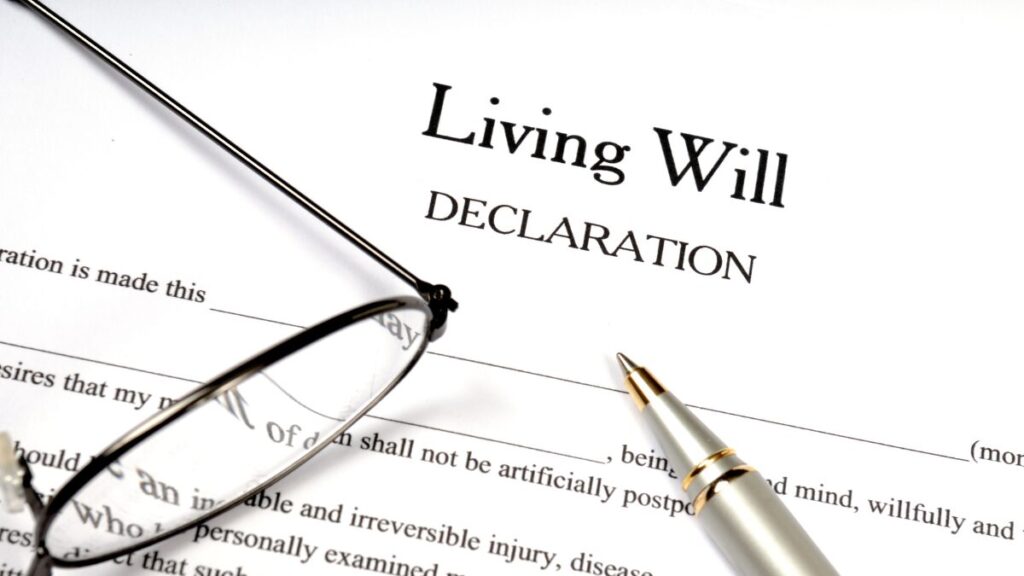
終末期での医療について自分の希望・意思を表した書面を「リビング・ウィル」と言いますが、普段からこうしたことをご家族と話し合い、「リビング・ウィル」を書いておくと、万一の時にご家族の葛藤も軽くすることができるでしょう。日本では長く死について話すことはタブーとされてきましたが、人生の終わりを考えることは今をどのように生きるかを考えることにもつながります。元気なうちに葬儀のことも含めて、ご家族と人生の終わりについて話し合ってみてはいかがでしょうか。